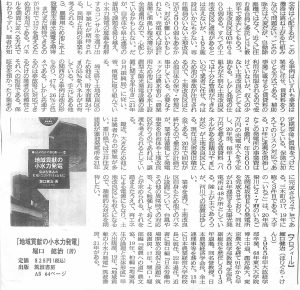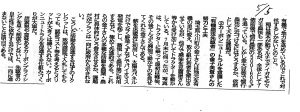もう少しすると本屋さんに出ると思います。法人経営、家族経営、いろいろな事例も紹介しているので、参考にしてください。最近は外国人を含め、いろいろな形で雇用を受け入れ、経営を拡大したり強化している経営体が多いです。それが、家族経営だと、後継者を確保するのにつながったり、経営の質的な充実になっています。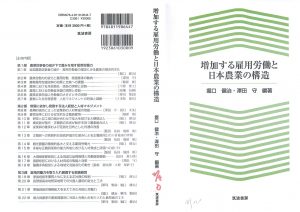
アーカイブ
技能実習制度、特定技能の見直しについて堀口の見解を新聞に載せました。
政府が見直しの議論を始めたので、堀口も実態調査や共同研究を基礎にして、意見を表明しました。日本農業新聞11月20日号の「現場からの農村学教室」です。実際の記事は、テーマが「日本の人材育成型外国人受け入れ」、メインの見出しは「在留の制度拡充が鍵」、小見出しは、「影響を考慮し数定める」「労基法の順守を徹底」になっていますが、本文はほとんど変わりありません。
20221103技能実習から特定技能への展開にみる日本独自の人材育成型外国人受け入れの仕組み早稲田大学名誉教授・堀口健治

日本農業新聞に外国人と日本農業のことを寄稿しました。
9月20日号です。前の法務大臣が技能実習制度のことに触れ、抜本的な見直しが必要と述べて、すぐに日経新聞、朝日新聞、が同調し、歓迎しています。しかしこれは前から指摘しているのですが、間違いです。技能実習制度が実際にどのように使われ、彼らがどのように働き、また研修しているか、そして労働基準法に守られた雇用労働者であり、研修手当という安い手当てでないことは調べればすぐわかるのですが・・・・現場の調査に出ていません。駆け込み寺の現場は見ているのでしょうが、それだけです。
駆け込み寺や、契約を守らない経営者がいることとかは、大いに報道してそれを直させねばなりません。しかし、多くは技能実習制度の趣旨を守り、雇用契約が守られています。制度が間違っているからそれが発生するという論理は、あたっていません。実習、研修は、日本人と同じ仕事をしながら、on the job training で学び、しかも給与は、同じです。実習と雇用労働とは、仕組みとして一体になっています。
中国地域にある大手企業が、日本人の嫌う仕事のみを実習生に3年間やらせ続けたので、実習機構から違反を指摘され、改定を求められました。研修のためには各種の仕事を計画通りにしなければならないのです。
またシンブルな雇用労働である韓国を望ましい制度という議論がありますが、最近(2021年5月14日)、三菱UFJリサーチ&コンサルティングが「現地調査からみた韓国・雇用許可制度の実態」として、日本と違い韓国は「フロントドア」から入れても、借金はあるし、失踪率は高いことを明らかにしています。日本は「サイドドア」だから、不正が多い、ということは間違いになるのですね。
堀口は、日本が研修で入れるのはサイドドアと思いませんし、日本の技能実習の仕組みは、研修と雇用、とが一体になっています。
日本は最近の失踪率が1-2%になっていますが、この中にはブローカーに騙されているのも含まれ、雇用主のひどい扱いで逃げてきた、という事例だけではありません。借入金も関係者の努力で、減ってきています。実態を踏まえたうえで、議論をする必要があります。
不熟練労働力を受け入れる日本独特の技能実習制度について実際と機能を学会誌に書きました。
残念ながら技能実習制度という言葉を聞くだけで、人権侵害、「奴隷労働」を語る人がいるようですが、コロナを経ても、来日してくれる、手が上がるということは、そうではなくて、来てくれる人にとってメリットがあるのですね。
雇用契約を結び、かつ on the job training なので、形式と実態が矛盾することはありません。帰国後は半分は元の会社に戻り経験を生かしているようです。しかし日本の実習は、細かな職種指定なので、帰国後にそれにぴったり合う仕事が直ぐに見つからないことも事実です。しかし、実態調査をすると、日系企業(途上国では多くが現地の大卒者が就職し、技能実習に来るような高卒以下の若者には採用の機会がありません)で、彼らが実習の経験を活かして多く働いており、またカンボジアでは日本語学校の教員になっている人にも多く会いました。これらも技能実習の研修の成果が生きているといえます。
一部にみられる人権侵害は、摘発・改善すべきですが、制度そのものが全体として、どのように機能しているか、まずは実状を広く把握する必要があります。前法務大臣が技能実習制度そのものが悪の根源で抜本的に見直す、という発言は、誤解を招くもので、実態をまずは正確に把握すべきだと思います。
日本地域政策研究、という日本地域政策学会の機関誌で直近の28号(2022年3月25日)
に、「農業分野における外国人労働力導入の現況と研究視座」で、全体の概観と色々な人の研究業績を紹介しました。実際とその機能を理解するのに、便利なものになると自負しています。ネット検索で、「日本地域政策研究学会」を探していただき、機関誌のところをクリックすると、どなたでもPDFで読むことができます。
「ため池に太陽光パネルを敷く」を土地改良新聞2022年8月25日号に書きました。
再生エネルギー・カーボンニュートラルの実践的研究を始めました。
広島で既存の小水力発電に動きがありそうです。
古くから稼働している小水力発電、広島県には多くあります。堀口としては固定買取にぜひ載せてほしい・・・しかしいろいろな事情で前に進んでいないように見えますが・・・
色々な工夫がなされているようで、9月以降には紹介ができると期待しています。
「農業分野における外国人労働力導入の現況と研究視座」を書きました。
軍司・堀口の共著ですが、2022年3月、日本地域政策学会誌『日本地域政策研究』28号に載りました。
この雑誌は、ネット検索で探し、該当号で論文をクリックすれば、内容を読むことができます。
いまだに農業分野での外国人労働力を単純労働力のみと思い込んでいる人が多いようですが、技能実習3号そして特定技能1号の人は、雇用先でチームリーダーになったり、準幹部になっている人が多く、経営にとって重要な役割についています。さらに技術・人文知識・国際業務の「技人国ビザ」(技術ビザとかエンジニアビザとも)の人も増えています。日本人幹部と同じ位置で、給与水準も高く、また技能実習生の寮とは分けているところも多いです。
彼らの役割は、堀口「ヒラ(技能実習ビザ)から幹部(技術ビザ)にも広がる外国人労働力―農業通年雇用者不足下の外国人の急速な量的質的拡大―」『農業経済研究』91巻3号、2019年で説明しているように、多くの労働者を確保する量的な充足の人だけではなく、質的にも必要な人材として位置づけられています。とくに2019年に導入された特定技能1号は、農業分野では技能実習生を経験して技能や日本語の一定のレベルを踏まえた人が多いので、リーダーや幹部に就く人が目立ちます。
また検討されていますが、特定技能2号に農業も加わった場合、この選択肢は外国人、雇用する経営者、双方にとり、新たな雇用の位置づけをもたらすと思われます。注目する必要があります。
3月30日、日本農業経営大学校の校長理事を引きました。これからは名誉教授として研究調査に関わります。
就農を目指す若者の教育に、この8年間、携われたことは、大学教育と異なる新たな経験で、私にとって勉強になりました。実践的な教育ですね。農地法の解説を大学で長らくしていましたが、彼らには農地の出し手を探し出し、関係する法律や仕組みを知ったうえで、契約の内容を検討させました。果樹に新規参入する場合、借地であれば契約期間の短さは後に問題になるし、農地中間管理機構を経由することで地主さんに10年を認識してもらうなど、いろいろ考えました。またこの法律はどのような意義を持つか、農地法体制の仕組みも実践的に学んでもらいました。
卒業生の紹介は、堀口・堀部編『就農への道』農文協・2019年、で新規独立就農、親元就農、雇用就農と、いろいろなタイプを説明できましたし、また青年就農給付金をいかに有効に使うか、実例の話が出来たのはうれしい限りです。
農業版MBAの仕組みをモデルとして、この学校では出来たのではないかと思いますが、これからは受講生がより受けやすい形を考えてもらいながら、再発足を期待したいと思います。
堀口は、今までも続けていた研究を継続します。再エネの一環で小水力発電をさらに増やしたいし、農業・農村でのカーボンニュートラルの研究を進めたいですね。また日本農業の構造的な研究として、雇われ労働力の重要なパートを占める外国人、彼らの実際の役割や日本農業への貢献を正確に把握する必要があります。彼らのおかげで、家族経営に後継者が定着したし、法人では大型機械を操縦しながら、日本人・外国人、ヒラの従業員のチームリーダーになっている外国人も多くみられるようになりました。
「農業者は長寿で元気」という実証的研究もさらに詳細にしたいです。堀口
農村と都市をむすぶ誌2月号で農業での雇用のいろいろな事例を紹介しています。
請負や派遣、いろいろな形があります。複数の執筆者で下記のように分担しました。
3か月しないと内容を全農林のホームページで読むことが出来ないので、今は雑誌を直接手に取っていただけるとありがたいです。
【時評】農業部門の労働力不足について(KY)
【特集】農業労働力調達にみる諸事例と組織的関与・支援の動向
不足する労働力を必死に集める産地の実情と工夫 堀口 健治
労働力確保の課題と全農おおいた方式
および特定地域づくり事業協同組合の展開 石田 一喜
ミカン地帯の短期収穫労働を支える「アルバイター事業」と従事者の特徴
−JAにしうわの取り組みからの検討− 岩﨑 真之介
援農ボランティアに見るJAの取組みとその内容
−JAの強みを生かした普及・定着に向けて− 草野 拓司
県域を対象とする農協系受入監理団体の実際とその役割
−茨城県エコ・リード− 軍司 聖嗣
長野県高冷地野菜地帯における技能実習生と
派遣の産地間移動特定技能外国人との混在 堀口 健治