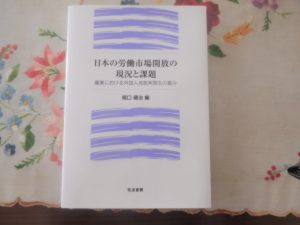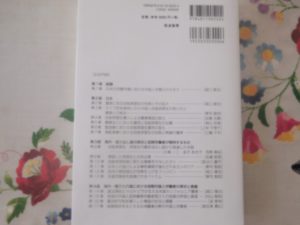下記のテーマで2018年4月から3年間、研究を仲間とともにすることが出来るようになりました。審査委員の判断に心から感謝したい。2017年11月に筑波書房から堀口編で出版した『日本の労働市場開放の現況と課題』も、科研費を3年間いただいた、その成果になります。
その科研費の後、2年間立て続けに科研費不採択で、名誉教授でも研究代表者の年齢に対する配慮があり難しいかな、と思いつつ、今回も応募しました。それが採択になったのです。本当に感謝・感謝です。
2012年の春にカリフォルニア大デイビス校での在外研究から帰国し、カリフォルニア農業へのメキシコ人労働者の役割の研究(マーティン教授等)に刺激され、日本でも大事な研究テーマとして加速させようと思い科研費に応募したのです。ある人は、「ヤバイ」問題(人権に関わる)なのでは・・・とのアドバイスもあったのですが、私は自分の主要な研究テーマのひとつに据えました。
上記の本を見れば分かっていただけますが、日本農業の労働力調達で外国人は重要な位置をすでに占めている。また雇用契約を結ぶ労働者であると同時に on the job training で研修する技能実習生、これに対して半年も前に現地で面接し来日後に発効する雇用契約を日本の農家が結び、日本の農家もコストを分担して半年以上の日本語事前研修や往復の飛行機代等を日本の農家が負担する状況を把握しました。
その後はサントリー文化財団に東大の安藤教授が応募し、ここに加わって2年間、研究をシンポを主に継続できました。その上で今回の科研費採択です。
テーマに見るように新たな視角を入れています。技能実習生、その人数が個々の経営にとっても増えるのに連れて、指導しチームとして作業するための人が、家族員では足りず、日本人常雇いの増加につながっています。こうした雇用の急速な変化を、雇用型経営の位置付けとして農業構造の研究に展開させたいと思っています。
そして受入国での外国人の導入が農業構造にどのような影響を与えているか、比較研究も目指しています。
「労働力編成における外国人の役割と農業構造の変動ー国内農業地域と韓台米英との比較ー」
シンポジウム「外国人技能実習生制度の改正と今後の行方」
1.趣旨 高齢化・人口減少の下、外国人技能実習生の導入が急増している一方、それに伴い様々な問 題が発生し、昨年度は制度改正が行われたところである。技能実習期間はこれまでの3年間か ら5年間に延長されたが、その適用条件は厳しいものとなっている。また、中国に代わってベ トナムが最大の送出し国になるなど、国際労働力移動という点でも大きな変化が生じている。
本シンポジウムの目的は、そうした最新の状況を把握し、シンポジウム参加者の間で情報を 共有するとともに、外国人技能実習生制度の今後の行方について議論を行うことにある。農業 だけではなく、漁業と製造業の実情についても報告をお願いするとともに、労働力問題の2人 の専門家からもコメントをいただくことにした。この問題にご関心をお持ちの皆様方にとって、 本シンポジウムが実り多きものとなることを期待している。
2.日時・場所 日時:2018年3月19 日(月)13:00~17:30(受付開始 12:30~)
場所:東京大学農学部弥生講堂アネックス(地下鉄南北線東大前駅下車・徒歩3分) 農学部正門を入ってすぐ左手の建物です。
3.報告内容とタイムスケジュール
13:00~13:05 開会挨拶:堀口健治(早稲田大学名誉教授)
13:05~13:15 趣旨説明:安藤光義(東京大学)
13:15~13:45 現時点の農業における外国人労働力の重みと技能法・戦略特区以降の変容 :堀口健治(早稲田大学名誉教授)
13:45~14:15 ベトナム国における外国人技能実習生送出しの実際と実習帰国者の動向 :軍司聖詞(早稲田大学非常勤)
14:15~14:45 漁船漁業における外国人技能実習生への依存と海技士不足 :佐々木貴文(鹿児島大学)
14:45~15:15 自動車部品製造業の技能実習生雇用:上林千恵子(法政大学)
15:15~15:30 休憩
15:30~15:45 コメント①(長期的視点からみた農業における技能実習生受入の変化) :松久勉(農林水産政策研究所)
15:45~16:00 コメント②(情報遮断下の安定) :加瀬和俊(帝京大学)
16:00~17:30 総合討論(司会:安藤光義)
4.問い合わせ先 東京大学大学院農学生命科学研究科・農政学研究室 安藤光義 TEL&FAX:03-5841-5322 E-mail:ando@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp
本シンポジウムはサントリー文化財団の後援を得て、東京大学と早稲田大学が共同開催する ものです。参加費は無料です。事前登録の必要もありません。 ご関心のある多くの皆さま方の参加をお待ちしています。
選考委員会の座長として大臣賞を沖縄県今帰仁村のあいあいファームに差し上げました。廃校の小中学校の施設を有効に使ったユニークな教育ファームです。プレゼンの写真にあるように活動は多彩です。地域の放棄地を借り受け、樹園地やハウスを経営し、色々なサービスにも取り組んでいます。
局長賞も写真の3事業者にさしあげたのですが、山形のサクランボ(やまがたさくらんぼファーム)、新潟のトマトとイチゴそしてレストラン(高儀農場)、金沢の麦芽やホップにまで自ら取り組む地ビール(わくわく手づくりファーム川北)、いずれも特長があり、いずれ、次の時期に大臣賞を狙ってくれるものと思います。


鹿児島大学勤務の時に、象グループの依頼で沖縄県今帰仁村の農業・農村調査を学生たちと行った。他の調査も並行してなされていたが、これらを踏まえて、彼らは風の通る開放型の公民館を建て、建築新人賞を受けたのである。堀口の名前も最後のところに載っている。40数年前の話である。
今回、6次化で受賞が決まった、あいあいファームを審査委員長として尋ねたが、その折に中央公民館を訪問できた次第。感激!
その当時、エアコンが付いた締め切り型の建物が増える中で、早大吉阪教授の流れを組む象グループは新しいコンセプトで公民館を建てた。その公民館は今も機能していることを確認できたのである。ただ当時屋根の上に展開していた蔦は、今は写真のように建物の端にのみにしか残っていなかった。屋根を痛めるため取り去ったのである。

劇場風の庭を取り囲む公民館の建物、そして廊下は外にあり、柱がフェンスではなくむしろ人々を受け入れる回廊になっていることにあらためて感激を覚えた。

場所は早大3号館4階の教室です。田中ゼミ出身の卒業生が集まって組織された、
「田中駒男先生を偲ぶ会」主催・政経学術院共催の形です。
田中駒男先生には堀口は大変お世話になりました。
偲ぶ会、の方々と一緒に仕事をさせていただいています。
実は堀口は訪問が始めてです。あまりにも有名なのに。沢山紹介したいのですが、今回は処理業者、受け入れ業者、の顔です。早い時期からバイオマス発電等取り組まれています。農事組合法人の発展を期待します。

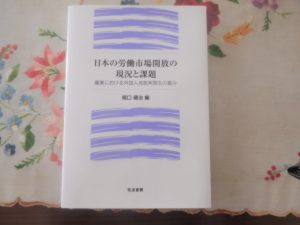
この5-6年、注力してきた日本農業と外国人技能実習生の研究成果が筑波書房から
出版されました。この11月から新技能実習法が施行され、また国家戦略特区での外国人農業就労が認められ、注目されています。科研費をもとにしたこの共同研究の成果は、実際はどのようなものか、双方にとってウィンウィンの関係ではないのか、送り出し国、受け入れの他の国等も訪問し、日本国内の代表的な地域をも調査したものです。是非読んでください。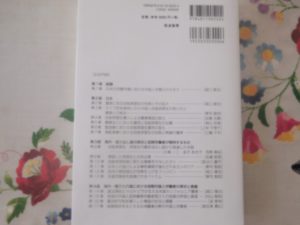
エクステンション本館屋上からもらい受けた土をバケツに入れ、稲を栽培。

ただこの写真は8月末です。刈り取り直前の写真、どこかにあるのですが・・・・整理が悪い。
左二つのバケツが毎年、受講生が丹精込めて有機肥料を入れ、混ぜ、展開してくれていた土です。野菜や稲が毎年大きく育っていました。そのおかげで、苗は同じなのですが、左はいいですね。右のバケツは従来の粘土質の土です。見るからに稲は貧相ですね。
農中総研の月刊誌ですが、堀口・弦間の共著論文が「自営農業者の長寿傾向と後期高齢者医療費への反映
―埼玉県本庄市における調査を踏まえて―」のタイトルで載りました。9月1日です。新聞と異なり、内容を十分に書くことが出来ました。参考にしてください。
サイトで、農林金融2017年9月号、のキーワードを入れて、検索ください。見ることが出来ます。
農業者は元気に長生き
2017年8月30日
農村部を歩くと、農作業に励む元気なお年寄りに多く出会う。農作業をしているから元気なのか、元気なお年寄りだけが農作業をしているのか-。この疑問に、農業経済系の研究者が農業者世帯などへのアンケートからある答えを導き出した。やはり、農業者には、病気知らずで長寿を全うする「ピンピンコロリ」の傾向がみられるという。 (白鳥龍也)
自慢の水田の手入れに訪れた山浦昭和さん=長野県小諸市で 写真
◆入院経験ゼロも多数 早稲田大研究
研究をまとめたのは、早稲田大政治経済学術院の堀口健治名誉教授と同大社会科学総合学術院の弦間(げんま)正彦教授。医療費削減の方策を探る目的で、農村部と住宅街が混在する埼玉県本庄市で、農業者とそれ以外の人を比較することにした。
農業者に関しては今年二月、農協の協力で組合員約三千九百世帯に調査票を配布。それ以外は三月、JR本庄駅周辺の住宅街の千九百世帯に同じ調査票を配った。有効回答は計約八百四十世帯分(うち農業者約五百四十世帯)。
アンケートでは一九八九年以降に亡くなった家族がいる場合(1)死亡年齢(2)生前の仕事と就労年数(3)引退年齢-などを質問。その結果、専業に近い形で農業をしていた男性の平均死亡年齢は約八十二歳、女性は約八十四歳で、それ以外より男性は約八年、女性で約二年長かった。引退年齢は男性が約七十四歳、女性が約七十三歳。男女ともそれ以外の人より約十年遅く、約五十年間働いたことになる。
引退から死亡までの年数は、農業者の男性は約八年、女性は約十一年で、それ以外の人と比べて男性は約二年、女性が約八年短かった。死因も、農業者はそれ以外よりも老衰の割合が高かった。
このほか、調査では六十五歳以上で農業をしている人には入院の経験がない人が多いことが判明。堀口名誉教授と弦間教授は「農業者には健康寿命(制限なく日常生活が送れる年齢)が長い特徴が出ている」と分析する。個人データにより、農業と長寿の関係を検証した研究は「他に例がないのでは」という。
「長寿の里」佐久地方のほぼ中心にある「ぴんころ地蔵」=長野県佐久市で 写真
◆長寿願う観光客、続々 長野・佐久「ぴんころ地蔵」
「寝たきりになりませんように」。白煙たなびく浅間山の南麓、長野県佐久市にある通称「ぴんころ地蔵」(正式名称は長寿地蔵尊)。観光バスなどでひっきりなしにやって来る参拝客が手を合わせたり、愛らしい顔をなでたりしている。
佐久地方は、男女とも長寿日本一の長野県でも、平均寿命が長い。地蔵は、地元商店街が建立した長寿の里のシンボルだ。
「忙しくて、病気になっている暇なんてなかったなあ」。佐久地方の一角、小諸市で六十六年間農業に携わる山浦昭和(あきかず)さん(84)は、血色のいい顔をほころばせた。三代続く専業農家の長男で、今でも水田とジャガイモ畑など約一ヘクタールをほぼ一人で切り盛りする。病気らしい病気は、三十代でなった盲腸炎くらい。
「好き嫌いなく食べ、日の出から日没まで夢中で働いた。酒はそこそこ。農地改良など、ムラ活性化のための仕事も率先してやってきた」。健康のこつと問われても特になく「気が付いたらこの年ですよ」。
農業と健康の関連について、佐久市立国保浅間総合病院の箕輪隆副院長(58)は「農業は中程度のスポーツを続けるのと同じ。水と空気が澄んだ農村で、新鮮な野菜や果物を食べられる影響も大きい」と話す。