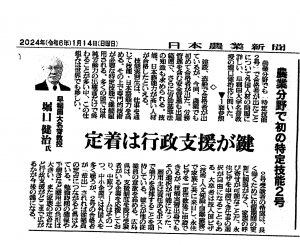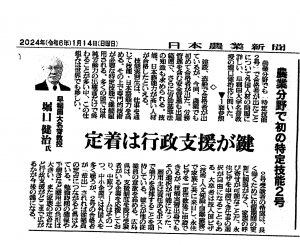https://www.ibi-japan.co.jp/gakkairengo/htdocs/web_publish/index.html
堀口以外の方の論文も載っているようなので重く、上記のサイトを開いても、文章が出てくるのが少し時間がかかります。
後日、J-Stageでも公開予定です。
堀口の論文タイトルは、「外国人がもたらす日本農業の構造変化」で、あまりこうした話題に触れる機会が少ない、一般経済学の学会会員にもわかるように書きました。
日本農業に貢献する外国人、その量と質を知ってもらいたい気持ちです。
学会誌に書くのは初めてかもしれない。一般雑誌等には書いていましたが、農業経営関係の学会誌で論文として書くのは初めて。研究者に、
この学際的な課題に積極的に関わってほしいと希望しています。
日本農業経営学会、のホームページに入っていただくと、最近号の学会誌に載っています。だれでもアクセスできます。
2025年1月18日・土曜の新聞ですが、アンケートに対する多数の合格者の回答、そして彼らを雇用する農業経営者のアンケートへの回答が、主だった集計だけですが、掲載されています。
これは、全国農業会議所のホームページに入っていただくと、新着情報で、このアンケートのことが載っています。新着情報から入り、次の画面では、関連資料が下部にあるので下の方にスクロールすると、関連資料のトップに、結構な量のある報告書、が出てきます。
是非、直接、読んでください。
特定技能2号合格者はビザを更新でき、家族を呼び寄せることができ、10年後には永住ビザの申請ができます。移民ともいえるこの仕組み、特定技能1号対象の人手不足産業では、一斉に2号試験が始まっていますが、合格者のアンケートは、我々が行ったものが初めてとみられます。
非常に重要な事柄だと思いますが、メデイアはほとんど、報道していません。
我々も社会発信、さらにしなければ、と思っています。
全国農業会議所のホームページには、新着情報が載っており、今日12月24日に、農業特定技能2号試験の合格者及びそれらの人を雇用している経営者、これ等の人(初回から5回目まで)にアンケートを送り、回収できた人について、我々が行った集計・分析が、長文ですが、載ったことが述べられています。
https://www.nca.or.jp/support/farmers/nogyosien/index.html
を使って、一気にホームページに入り、そこの「関係資料」の最後に、上記の長文が載っています。アンケートの集計の多くの表図が載っています。
合格者の多くが同じ企業に勤務を継続し、10年後には永住ビザを申請することを述べています。
ソーラシェアリング(営農型太陽光発電、とも)の、日本農業新聞での連載(5回予定)を、9月27日に第1回載せました。これは、石川県白山市にある美味しい清酒・手取川の蔵元の吉田酒店が、蔵前の酒米生産水田に垂直型のソーラーパネルを並べ、その電力を自家用に使っている様子です。所有する水田でコメを生産するだけでなく、自力で電気を起こしそれを工場に使うのが、非常にわかりやすい。
第2回は11月4日で、下記に載せます。non-Fitで、オフサイトPPAの事例です。1週間後は、何とか、補助金無しで自力生産できないか、検討している事例を紹介します。
https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n2409jo3.pdf
上記をコピーし、検索対象にしていただくと、上記の課題をまとめた論文を見ることができます。
なかなか、これに関する統計を見ることができません。集計がなされていない。
また、外国人がどのようなビザで農地等、経営者になる場合の要件を満たしているのか、
色々な事例があるようで、これ等もまずは事例調査で確認しました。
さらに研究・調査が必要と思われます。
https://peatix.com/event/4060188/view?k=121ec9160c9b9d01bff9b3f61bbfe3aec0cb71b4
有料が申し訳ないところですが、報告者、自身も含め、具体的な話をする予定です。参考になると思います。
自然エネルギー財団の最近の報告では、この太陽光発電は、堀口の理解は、営農型発電ですが、発電の種類の中では、コストが最安になってきているとの、話です。関係者の努力が実ってきた。
更なる普及をプッシュしたい。
7月初めに店頭販売です。テーマは、「営農型発電で電力を地産地消」です。
FITでは高い買取価格を目指すのみで、その電気がどこに流れ、どのように使われているか、の問題意識がありませんでした。
再エネ電気であることはよいのですが、それが電力会社のみに流れ、発生源である農業・農村には高い値段で地域の農業企業や中小企業に戻ってきていたのです。お金が都会に出っぱなしです。
これをやめ、地産・地消で、地域の経済に電気が使われるように、その実例を紹介しました。できるだけやさしく、写真も使いながら、説明しました。
仕組みはオフサイトPPAの仕組みです。急いで勉強する必要があります。
この夏は再び「沸騰する地球」なので、パネルを農地上に展開する営農型太陽光発電があらためて見直されるはずです。
是非申し込んで参加ください。自治体関係者が多いと思われますが、一般の方も参加できるのでよろしく。
現在の基本法の議論で、この分野の議論、また新しい法や政策に入っていないですね。
20240410シンポ5月10日農業・農村エネルギー自給戦略シンポ
日本農業新聞に載せました。2号はその意義が質的に異なります。
雇用者である農業経営者の期待、合格した人の期待がよくわかります。